2004年 国の年金改正の概要
|
| |
第159回通常国会で、年金制度改革法案が成立しました。
今回の年金改正の主旨は、2点あります。
| (1) |
社会経済と調和した持続可能な制度の構築と制度に対する信頼の確保 |
| |
現役世代の負担が過重にならないよう、かつ高齢者の生活を支えるにふさわしい給付水準を確保する、という二点のバランスをとり、国民が信頼できる持続可能な制度とする。 |
| (2) |
生き方、働き方の多様化に対応した制度の構築 |
| |
多様な生き方、働き方の選択に柔軟に対応し、それが年金制度上評価される仕組みとする。 |
| |
|
この改正の中から、皆さんの生活に直接かかわる主要な3点のテーマについてご紹介します。
青字部分が、今回の改正個所になります。
|
(1)保険料が今後段階的に引き上げられます
〜 厚生年金・国民年金保険料の変更〜 |
厚生年金と国民年金の将来の保険料水準を固定した上で、その収入の範囲内で給付水準を自動的に調整する仕組み、「保険料水準固定方式」が導入されます。これは年金給付と負担のバランスを調整するためといわれています。
今後2017年まで保険料率が引き上げられることになります。
|
| ●厚生年金保険料率を段階的に引き上げ(2004年10月から) |
| |
| 現在の厚生年金保険料率は13.58%(労使折半、以下同じ)です。 |
| 2004年10月より、毎年0.354%ずつ段階的に引き上げられ、2017年に18.30%に到達した後は、この水準で固定されます。 |
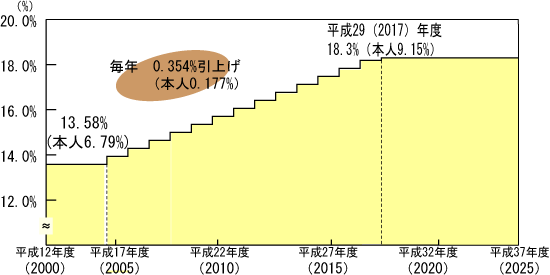
| ※厚生年金の保険料負担は、平均的な被保険者(月収36.0万円(ボーナスは年2回合計で月収3.6ヶ月分))の場合、毎年、保険料率の引上げにより、月650円程度(ボーナス1回につき1,150円程度)保険料負担(被保険者分)が増加します。 |
■国民年金も段階的に引き上げ(2005年4月から)
国民年金保険料(現在、月額13,300円)も、厚生年金保険料と同様に段階的に引き上げられます。
2005年4月から、毎年280円ずつ引き上げられ、2017年度に1万6,900円で固定されます。
(但しこの1万6,900円は2004年度価格です。経済情勢等が厚生労働省の試算と異なる場合は、金額が変動することがありえます。)
|
(2)年金額は経済動向にあわせて変動します
〜マクロ経済スライドの導入〜 |
◆2005年4月から、年金額の計算に、マクロ経済スライドが導入されます (2004年10月施行)
現在の年金額の改定には、賃金の上昇や物価の伸びが反映されています。
新たにマクロ経済スライドによる調整を導入することで、それらの伸びを予定では2023年度までに現役世代の平均的収入の50.2%(現在、59.3%)に抑えるとされています。
マクロ経済スライドとは、保険料を負担する現役世代の人口の減少や、平均余命の伸びなどの影響を年金額の改定に反映させることをいいます。
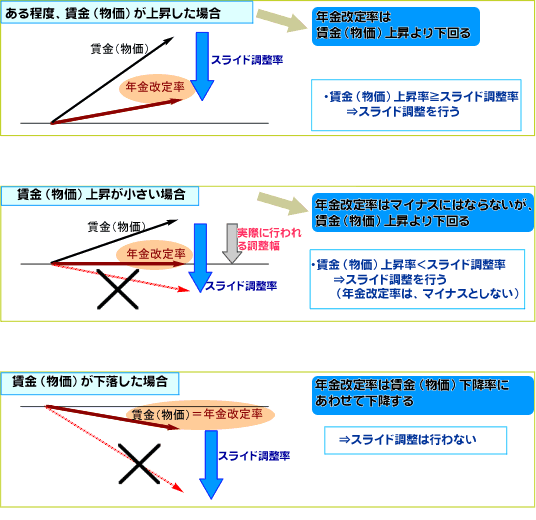
|
(3)多様な生き方・働き方に対応する年金制度へ
〜女性と年金・60歳からの年金など〜 |
●育児休業期間支援策を拡充(2005年4月から)
| (1) |
現行の育児休業の厚生年金保険料免除制度の期間は子供が1歳になるまでとなっています。
この期間が、2005年4月から子供が3歳になるまでに延長されます。 |
| (2) |
育児のために勤務時間が短縮されて、賃金が低下した場合に、休業前より保険料が低下した場合でも、年金額の計算上は育児休業期間前の水準で保険料が納付されたものとみなす制度が導入されます。これも2005年4月からの実施です。
(期間:子供が3歳になるまで) |
■未届け第3号被保険者の救済のための特例届出措置(2005年4月から)
国民年金の第3号被保険者(被扶養配偶者)の届出に漏れがあった場合、現行では過去2年間分については、届け出ることで保険料納付済み期間として年金額の計算に算入しています。
2005年4月からは、2年前の未届け期間も、特例届出によって納付済み期間と認められることになります。
●60歳から64歳の在職老齢年金の一律2割カットを廃止(2005年4月から)
現行では、60歳〜64歳で在職している場合、給与や年金額に関わらず、一律に年金額の2割を支給停止する仕組みとなっています(給与額の増加に応じて、支給額はさらに停止されます)
| (1) |
2005年4月から、この一律2割カットを廃止し、年金額と給与の合計額が一定の基準値を超えない限り、年金が全額支給されるようになります。 |
| (2) |
2007年4月から70歳以上の在職者についても、60歳代と同じように、給与額によって年金額が調整されます。(保険料負担はない。) |
●離婚時の厚生年金の分割(2007年4月から)
離婚した場合に、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を分割(上限は1/2)し、分割された記録に基づいて、夫婦それぞれに厚生年金が支給されるようになります。制度施行後の離婚が対象となりますが、施行前の婚姻期間中の納付記録も分割対象となります。
2008年4月からは、国民年金の第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合、その配偶者の厚生年金の2分の1を分割できるようになります。
|
|
|