キャッシュ・バランス・プランについて |
キャッシュ・バランス・プランは、確定給付企業年金法によって導入することができるようになったハイブリッド(混合)型の年金制度です。
確定給付年金と確定拠出年金の両制度の特徴を併せ持ち、両制度のデメリットを緩和し、メリットを活かすような仕組みとなっています。
代行返上後の新たな基金制度として、現在注目を浴びています。
キャッシュ・バランス・プランは、想定利回りを設定し、企業が資産を運用するという確定給付型の仕組みに、給付額の決定に運用結果による変動を反映させる確定拠出年金の特徴を組み入れた制度です。
キャッシュ・バランス・プランを導入すると、まず加入員一人ひとりに対し自分の口座(仮想口座)をつくり、この口座に毎月定められた額を基金が積み立ててゆきます。そしてこの積立金に毎年一定の利息を付与し、最終的に積立金元本とその利息の合計額が加入員の年金の原資となります。
個々人ごとに口座を持つというのは確定拠出年金のようですが、キャッシュ・バランス・プランの場合は、基金が資産を運用するので、口座は仮想のものとなります。
利息の決定に際しての想定利回りは、一定の指標(客観的な経済指標となりえるもの)を採用します。また、この際に最低保証利率を設定します。
確定拠出年金のように、運用の結果によって年金の額は変動しますが、実際の運用結果が悪くとも、一定の給付水準は保証するという、確定給付年金の特徴も併せ持っています。
年金額は、決められた指標に基づいた年金給付利率により、毎年変動します。無論この場合も、一定の給付水準は保証されています。
加入員側からすれば、確定拠出年金のように、運用結果が好調であれば年金額の増加が見込める一方で、従来の厚生年金基金のように、一定の給付の保証がある点がメリットといえます。
また企業側としては、運用環境が悪化した際でも、指標利率が運用環境等にあわせて変動するため、比較的退職給付債務の増加が抑えられる傾向にある点がメリットです。
|
|
|
|
|
|
想定利回りは、客観的かつ合理的に予測可能なものであり、ある程度安定的なものを指標として用いることができます。具体的には以下の4つが可能となっています。想定利回りはゼロを下回ることはできません。
| 想定利回りの例 |
| (1) 定率 |
| 例: 2.5% |
| (2) 国債等の利回り |
| 例: 10年国債の過去1年平均 |
| (3) (1)と(2)の組み合わせ |
| 例: 10年国債の過去1年平均+1% |
(4) (2)又は(3)に上下限を定めたもの
|
| 例: 10年国債の過去1年平均+1%、上限5.5%、下限2.0% |
|
|
|
毎年、個人毎に「基準給与×一定率」などで付与された額に一定の基準によって設定された想定利回りを付した額が付与されます。その累積額を確認できることによって、現時点での残高を把握できるしくみとなっています。
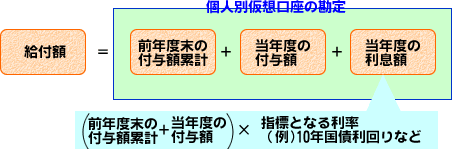
※利息が付与される対象に、当年度の付与額が含まれない場合もあります。(規約によって決定されます)
|
| 資産運用の流れ(例)(利息が付与額の合計に対して適用された場合) |
|
|
前年度末の
累計額
|
個人ごとの
付与額
|
付与額の合計
|
想定
運用
利回り
|
実際の
運用
利回り
|
適用される
運用
利回り
|
運用収益
|
累計額
|
|
1年目
|
-
|
10,000
|
10,000
|
2.0%
|
2.0%
|
2.0%
|
200
|
10,200
|
|
2年目
|
10,200
|
10,000
|
20,200
|
2.0%
|
3.0%
|
3.0%
|
606
|
|
|
3年目
|
20,806
|
10,000
|
|
2.5%
|
−1.0%
|
2.5%
|
770
|
31,576
|
|
4年目
|
31,576
|
10,000
|
41,576
|
2.5%
|
2.5%
|
2.5%
|
1,039
|
42,615
|
|
毎年、個人ごとの仮想口座に一定額が付与され(例では毎年同額としてありますが、給与等と連動する場合もあります)、それに、その年の運用による収益が付加されてゆきます。
想定運用利回りの決定方法は、固定型や、国債等に連動した変動型がありますが、例では変動型をとっています。
表中2年目のように、実際の運用利回りが想定利回りを上回った場合は、加入員に分配され、逆に表中3年目のように想定利回りを下回った場合は、基金が補填し、想定利回りは確保される仕組みとなっています。
|
|
|
|
キャッシュ・バランス・プランのバリエーションとして、キャッシュ・バランス・プラン類似制度も、平成15年5月以降、導入可能となりました。
この類似制度は、 在職中は従来の制度のままとし、受給権者になってからは、キャッシュ・バランス・プランと同様に年金額を指標に連動させるという制度です。 |
 |
| |
 |
|