| 確定拠出年金について |
| |
| ◆確定拠出年金制度は、現役時代の運用結果によって、将来の年金額が決まる年金制度です |
2001年6月、国会で確定拠出年金法案が成立し、2001年10月から各企業で確定拠出年金制度の導入が可能になりました。
|
| |
| |
| ●確定拠出年金(企業型)の概要 |
|
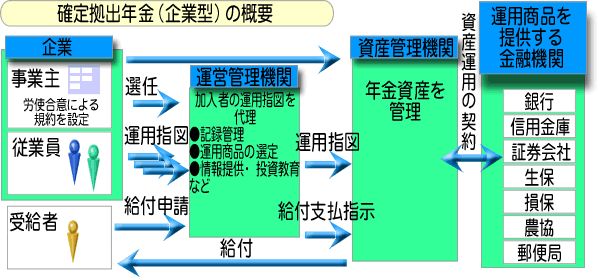
|
●確定拠出年金運用のポイント
確定拠出年金は、加入者自身が運用の指図を行う点が最も大きな特徴です。
これまでの企業年金は確定給付年金といい、掛金の額や加入期間などによって将来の給付額が決まってくる年金でした。資金の運用も、予定利率を決めて、基金が金融機関に委託して行っていました。
しかし確定拠出年金は、運用において全面的に個人の意思が反映されます。どの金融商品にどのくらい配分するのか、などを自分で決め、将来の年金額はその運用結果によって決まります。ですから、運用にあたっては、自分で納得した上で判断するという「自己責任」がもっとも大切なことになります。
|
| |
●運用の心得
|
●運用する金融商品は
確定拠出年金の資産を運用する金融商品は、預金、投資信託、株式、保険をはじめ、いずれも流動性があり、時価による評価ができる商品になります。不動産は対象になりません。
実際には、運営管理機関から3つ以上の金融商品が提示されますが、その中には元本が確保されるリスクの低い商品も必ず含まれることになっています。その中から自分で判断して運用商品を決めることになります。1つの商品でもいいし、複数の商品を選ぶこともできます。法律では、提示する金融商品の種類として、下記の商品が決められています。 |
| |
|
|
| A |
元本確保商品 |
預貯金/金融債/金銭信託/貸付信託(預金保険制度などの対象になるもの)/国債/地方債/政府保証債/利率保証型積立生命保険/積立傷害保険(損保)/定期年金保険(簡保)など |
| B |
一般の運用商品 |
投資信託/投資法人の投資証券/公共法人債/外国の公共債/変額保険など |
| C |
1つの銘柄による
運用商品 |
個別社債/個別株式など |
|
|